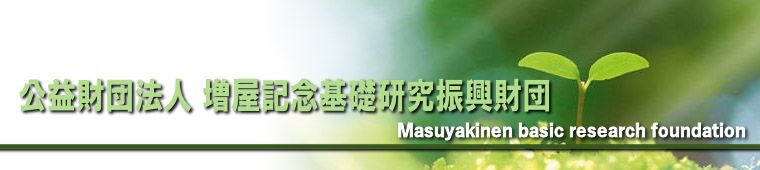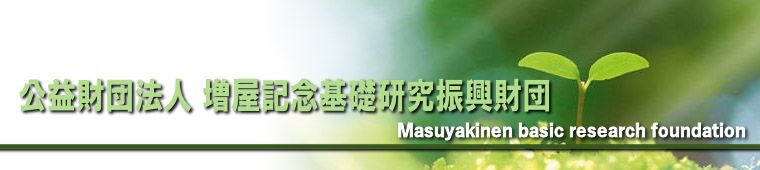01 京都工芸繊維大学 分子化学系 山田重之 准教授
テーマ:「室温領域で流動性と分子配向秩序を併せもつ液品性有機半導体の開発」
本研究では、πスタッキングを促進する電子不足芳香環として四フッ素化トラン型のD-π-A 構造メソゲンを採用し、室温付近でも安定にSmA相を形成できるよう、長鎖アルコキシ基を導入した棒状分子を開発した。具体的には,イミダゾール環を有するフッ素化芳香環を基盤とした四フッ素化トラン型メソゲンの逆末端に長鎖アルコキシ基を導入した化合物を合成した。さらに、メチルイミダゾリウムヨージドをEWG とした四フッ素化トラン誘導体や、PF6-やNTf2方を対アニオンとした誘導体も合成した。相転移挙動の評価から、イミダゾール環を有するフッ素化トラン誘導体のうち、C10H21O からC12H25O 基を有する化合物では、モノトロピックなネマチック相を形成することが明らかになった。また,I- やPF6-を対アニオンとするイミダゾリウム塩は融点が高く、一部で熱分解が認められた。一方、NTf2方を有するイミダゾリウム塩では,長鎖柔軟鎖を導入することにより,室温領域を含む低温範囲で安定なSmA 相の形成が確認された。
02 大阪大学 大学院理学研究科 化学専攻 畑中翼 助教
テーマ:「天然から着想を得た環状多核錯体によるポリマ一分解」
近年問題となっている使用済みプラスチックの再資源化に向けて、ポリエチレンやポリプロピレンといった安定な高分子材料を分解・修飾する新しい手法の開発を試みた。生体内で炭化水素の酸化を行う金属酵素の仕組みに着想を得て、2つの銅原子を有する金属錯体を触媒として設計した。その結果、モデル化合物として用いたシクロヘキサンやヘキサンの官能基化反応に対して極めて高い活性と耐久性を示す錯体を得ることに成功した。この触媒をポリオレフィン材料に応用したところ、高温条件下でも安定に作用し、炭素-炭素結合の切断や酸素官能基の導入といった反応が効率的に進行した。本研究は、廃プラスチックから高付加価値な化学製品を生み出す新たな基盤技術として期待されるものである。
03 兵庫県立大学 大学院理学研究科 物質反応論Ⅱ講座 三宅由寛 教授
テーマ:「水素結合性有機構造体を用いたナトリウム二次電池の開発」
リチウム電池は現代生活に不可欠だが、リチウム資源の高コストと偏在が課題であり、代替材料として豊富なナトリウムの活用が注目されている。
しかしナトリウムイオンは大きく、輸送が困難という欠点がある。本研究では、ピリジン縮環π共役化合物の一種である2,7-ジアザピレンを主骨格に持つ水素結合性有機構造体を合成し、24 A×22 A の一次元チャネルを有する多孔性材料であることを明らかにした。空孔サイズはナトリウムイオンの貯蔵に適した構造を持ち、ナトリウム電池へと適用できることを見いだした。
04 立命館大学 理工学部電気電子工学科 半導体材料科学研究室 荒木努 教授
テーマ:「ワイドギャップ半導体 窒化アルミニウムの結晶成長技術開発」
本研究では、RF-MBE法およびDERI法を用いたAlN結晶成長について検討した。700 ℃成長ではA1リッチ条件下で平坦かつ高品質なAlNが得られたが、Al過剰により表面荒れが発生することも確認された。300 ℃成長では、成長時間短縮によりAl層混入を防ぎ、結晶性向上が可能であることが示唆された。DERI法では、MRGP とDEP の制御が結晶品質に大きく影響することがわかり、特にMRGPのAl/N比や時間、DEP時間の最適化が重要であると結論づけた。今後はこれらの知見を活かし、さらに高品質なAlN成膜技術の確立を目指す。
05 京都大学 大学院工学研究科 磁性物理学研究室 和氣剛 助教
テーマ:「Mg ドープによる希土類遷移金属磁性材料の性能改善」
Mg含有遷移金属磁性体の探索を行い、RMgC04 (R =
Ce, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu)でCl 5/C15bラーベス化合物を得ることに成功した。得られた試料の磁性を評価したところ、室温以上に転移温度を有する強(フェリ)磁性体であることが判明した。Rが磁性を有する場合には、フェリ磁性を示唆する補償温度が観測された。(Y1-xMgr)Co2 固溶系の検酎も行いⅹ= 0-0.5の範囲でC15/15b型のラーベス構造を有し、0.4あたりから秩序構造のC15b になることがわかった。Mg 含有遷移金属化合物の開拓を容易にするために、金属箔への封入法についても検討を行った。
06 大阪大学 大学院理学研究科 物理学専攻 塩貝純一 准教授
テーマ:「新しい薄膜積層法を用いた高効率熱電変換素子の開発」
本研究では、熱電材料として近年注目を集めているAgCrSe2のパルスレーザー堆積法による薄膜成長に取り組んだ。x 線回折及び走査型透過電子顕微鏡を用いた詳細な構造評価により、イットリア安定化ジルコニア基板がエピタキシャル成長に有効であること、出発原料にAg-rich のターゲットを用いることでAg欠損相を抑制できることを見出し、AgCrSe2単相薄膜のエピタキシャル成長に初めて成功した。今後、本研究で得られた高品質AgCrSe2薄膜の物性評価を進め、本物質特有の熱電特性や素子機能の創出研究に取り組みたい。
07 奈良先端科学技術大学院大学 データ駆動型サイエンス創造センター
赤瀬善太郎 特任准教授
テーマ:「次世代半導体デバイスのための高精度なマルチモーダル三次元顕微解析技術の開発」
本研究では、先端半導体デバイスにおける微量不純物の三次元分布を高精度に分析する新たなマルチモーダル計測法の開発を目的とし、アトムプローブ(3DAP) と電子線トモグラフィー(ET) という異なる顕微法の統合解析手法を構築した。3DAP は高感度な元素分布情報取得が可能だが、三次元再構成像の歪みが課題であり、ET は構造情報の取得に優れるが感度が劣る。本研究では、医用画像分野で用いられる非剛体レジストレーション技術を応用し、進化的アルゴリズムとBスプライン変形を組み合わせることで、3DAPデータをET データに高精度で位置合わせする手法を開発した。実験では、AlGaN/AlN/GaN
試料を用いて各種データを取得し、三次元再構築と手法の実証を行った。これにより、異種顕微データの統合に関する技術的課題を明らかにし、将来的な高精度三次元解析の基盤を築いた。
08 大阪大学 大学院薬学研究科 生体機能構造分析学分野 淺原時泰 准教授
テーマ:「ハロゲン系炭化水素類の光改質アップサイクルに基づく機能材料創製」
工業プロセスにおいて余剰生産されているハロゲン化有機化合物類に対して、独自の二酸化塩素光酸化を行った。 これにより、反応系中で活性な酸クロリド中間体を発生させ、種々の求核剤との反応により医薬品原料へと変換するケミカルアップサイクル技術を開発した。
これまで熱処理によって処分されていたハロゲン化有機化合物を直接的に有用化合物へと変換することができ、新たなケミカルアップサイクル法として、排出CO2削減、環境負荷の低減と言った観点からの社会貢献が期待される。
09 大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻物理有機化学講座 燒山佑美
准教授
テーマ:「フッ素置換お椀型分子からなる省エネルギー純有機誘電性結晶開発」
曲面π共役分子フルオロスマネン類について結晶内フッ素配列の制御を行い、得られた結晶の物性評価により、結晶化手法を変えるだけで低誘電~高誘電特性に加え、強誘電性や圧電性を示すことのできる多機能・省エネルギーな有機結晶材料を確立することを目的に研究を行った。
極性結晶の作成にあたり、まず結晶化用セルとして、φ1 cm の円形の穴を開けた1mm シリコンゴムシートを貼り付けたITO
ガラス電極を準備し、その内部にF-Sum 溶液と支持電解質からなる結晶化母液を加え、定電流装置を用い電場下で結晶化を行った。その結果、シリコンシートの端部に無色透明な結晶が析出したものの、質が悪く X 線結晶構造解析には至らなかった。またシリコンシートの耐薬品性が十分でなく、使用できる溶媒系が極めて限られてしまったため、透過性フッ素樹脂を用い、内部容量の自在変換・溶媒濃縮のための制御機構を新たに組み込んだセルを再設計することとした。現在その作成を進めており、まもなくの完成を予定している。
10 大阪大学 大学院薬学研究科 医薬合成化学分野 有澤光弘 教授
テーマ:「カーボンニュートラルに資する省電力的化学反応技術の創出」
本研究は、つい最近申請者らが開発した連続照射マイクロ波の技術を用いて、有用化合物の省電力合成法を確立するものである。下の研究を推進した結果、含フッ素化合物がマイクロ波を吸収し、反応に影響を与えるという萌芽的データを得た。
・マイクロ波の効果 (非熱的効果·熱的効果の切り分けを含む) に関する学理検証
(有機化学実験からのアプローチ) と新反応開発
・マイクロ波の効果 (非熱的効果·熱的効果の切り分けを含む) に関する学理検証
(核磁気共鳴装置およびX線吸収微細構造解析装置からのアプローチ)
・マイクロ波の効果に関する学理検証 (計算化学からのアプローチ)
11 大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 精密合成化学講座 武田洋平
准教授
テーマ:「汎用元素から成る高効率な近赤外発光有機材料の創出」
申請者は、有機NIR 発光材料の課題である低効率.低溶解性の解決に向け、TADF 機能を持つ分子の開発に取り組んだ。独自の酸化的骨格転位を活用し、sp2窒素を導入した新規電子欠損性化合物やD- A- D 型分子の合成に成功した。得られた分子は溶液中で700mn超のNIR 発光、固体中で650mn付近のTADF
発光を示した。現時点で明確なNIR-TADF 発光は得られていないが、今後の分子設計に向けた有望な手がかりを得た。
12 大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 布谷直義 助教
テーマ:「廃棄グリセリンのアップサイクルを可能にする新規酸化触媒」
グリセリンは、バイオディーゼル製造過程で副生するために供給過剰状態であり、廃棄処理が問題となっている。本研究では、グリセリンを有用化合物へとアップサイクルするため、格子内酸素を活性点へと効率的に供給できる助触媒に着目した新規触媒を創成した。
このような助触媒材料として、スクルーティニアイ ト型構造を有するZrSn0.9Bi0.1O4-δを新たに創成した。これを、白金とともにメソポーラスシリカに担持した触媒とし、常圧(大気開放) 、30℃ 、8時間の条件でグリセリン酸化反応を行った結果、有用化合物であるヒドロキシピルビン酸を収率58.0% (グリセリン転化率:98.8%) で生成できることが明らかになった。 この収率は、一般的な触媒 (ヒドロキシピルビン酸収率:数%) と比較して極めて高く、本触媒は優れたヒドロキシピルビン酸生成能を有することがわかった。
13 大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 佐伯昭紀研究室 石割文崇
講師
テーマ:「電荷輸送特性に優れた"二面性"インダセノジチオフェンの開発とデバイス応用」
キラルな物理量であるスピン偏極電流が,ホモキラル物質中でスピンの向きに応じてそれぞれ異なる値を示すCI SS (Chirality- Induced Spin Selectivity : 不斉誘起スピン選択性) は,近年大きな興味が持たれている物理現象である。キラル材料の中でも,キラルなπ共役ポリマーは,スピンコートなどの簡単な方法で良質な薄膜を形成できるため,スピンフィルター材料としても有用と考えられるが,これまでに高いスピン偏極率は観測されてこなかった。今回筆者らは,高い電荷輸送特性を示すインダセノジチオフェン (IDT) 骨格中のsp3炭素原子が不斉中心となる 「二面性キラルIDT 骨格」 を含むキラルなπ共役ポリマーを開発し,そのスピンコート薄膜が約70%のスピン偏極率を持つスピンフィルターとして機能することを見いだした。
14 大阪大学 大学院工学研究科 フューチャーイノベーションセンター 寺川成海 助教
テーマ:「高温量子異常ホール効果の実現に向けた原子層ハライド磁性体
/トポロジカル絶縁体ヘテロ構造の作製と界面電子状態の解明」
本研究では、層状磁性体である塩化鉄(FeCh)を数原子層の厚さしかない超薄膜としてビスマス(Bi)表面上にエピタキシャル成長させ、その電子構造と磁性を明らかにした。電子構造について、FeCh 由来のバンドは層数によらず絶縁体的であることが角度分解光電子分光(ARPES)実験からわかった。そのバンドギャップ中には、Bi の表面状態に由来しFeCb 層による電荷移動とモアレポテンシャルによる変調を受けた金属的な界面状態が現れることをARPES実験と強束縛近似による計算から明らかにした。磁性については、X 線磁気円二色性実験から、FeCh 超薄膜の磁化容易軸が2層以上では固体FeCh と同様に層垂直方向であるが、単層では層平行方向に変化し、それがFe3d電子の軌道磁気モーメントの異方性の変化に起因することがわかった。本研究成果は非磁性物質が接合する原子層磁性体の磁気異方性を制御しうることを示しており、ヘテロ積層物質のスピントロニクス応用において新たな道筋を示すものである。
15 京都工芸繊維大学 繊維学系 バイオベースマテリアル化学研究室 青木隆史 准教授
テーマ:「天然廃棄物から得られるDNAを素材として活用した機能性材料」
廃棄物となっている鮭の精巣組織から精製されたDNAを天然素材として利用した、機能性材料研究を行っている。本研究課題では、DNAの構造上の特徴であるアニオン性を利用して、カチオン性界面活性剤とのイオンコンプレックスを調製し、そのフィルムの物性について検討した。カチオン性界面活性剤は、hexadecylpyridinium chloride (HDPyCI) ( または慣用名が cetylpyridinium chloride, CPC) とhexadecyltrimethylammonium bromide (HDTMABr)である。 これら2種類の界面活性剤は、ともにヘキサデシル基をテール部位に有し、カチオン基がそれぞれピリジニウム(Py)基とトリメチルアンモニウム(Tm)基から構成されている。HDPyCI とNa-DNA とのイオンコンプレックス(D-HPy)フィルムと、HDTMABr とNa-DNA とのイオンコンプレックス(D-HTm) フィルムをそれぞれ低級アルコール溶液から調製し、それらの構造と物性を調べた。その結果、D-HPy フィルムのほうが、より柔軟性や高延伸性を示すことがわかった。カチオン基の種類により異なるイオン対形成能が生じることにより、フィルム全体の構造や物性に顕著な影響を与えることが明らかとなった。
16 京都大学 大学院工学研究科 機械理工学専攻
機械力学講座機械機能要素工学研究室 安達眞聡 助教
テーマ:「太陽光発電パネルの発電量回復を実現するための磁気クリーニングシステム」
太陽光発電システムを長期運用する中で生じる問題の1 つが,工場等から空気中に放出される微細な鉄粒子が付近の太陽光発電パネル表面に堆積して,太陽光入射を妨げることで発電量を低下させる問題である.その解決策として,本研究では磁気力を利用した独自の太陽光発電パネルクリーニングシステムを開発した.このシステムは,ユニークな磁極配置を持つ永久磁石の磁気ロールとその周囲を自由に動くことができる非磁性スリープから構成されている.磁気力を利用した粒子の捕捉機能と,遠心力を利用した捕捉粒子の分離による自浄機能を備えている.本研究では,装置側の各種条件や粒子側条件 (e.g. 透磁率,粒径) を変化させて粒子除去試験を行い,その結果を理論計算と比較することで,その粒子除去性能に関する基礎的特性を明らかにした.
17 大阪大学 大学院基礎工学研究科 物質創成専攻 機能物質化学領域合成化学講座
鷹谷絢 教授
テーマ:「遷移金属ハイブリッド触媒による光化学的二酸化炭素固定化反応の開発」
酸化還元活性な遷移金属であるルテニウムを導入した 「遷移金属ハイブリッ ド触媒」
(Ru-Pd 錯体)の合成に成功し,これを触媒として用いることで,二酸化炭素の一酸化炭素への光還元反応が進行することを明らかとした。本触媒は既存の単一錯体触媒と比較して一桁以上高い触媒活性 (TOF = 235 h-1) を示す。また,触媒活性能向上を目指し,パラジウムの代わりにその他の遷移金属を導入した二核錯体の合成と構造解析にも成功した。これらの結果は,異種金属二核錯体が,光増感能と二酸化炭素還元能を併せ持つ高活性複合機能触媒として機能することを実証したものであり,従来の人工光合成触媒とは全く異なる新しい触媒設計指針を提示したものとして重要な知見である。
18 神戸大学 工学研究科 先端機能創成学講座 上杉晃生 助教
テーマ:「シリコン微細構造の積層型熱電発電モジュールの開発」
本研究では,環境負荷が小さく,高い温度域まで使用可能な熱電発電モジュールの実現に向けて,ガラスーシリコン接合体で構成される発電モジュールの開発を行った。提案モジュールでは,シリコン層とガラス層とを合わせて約0. 5 mm の厚さを持つ発電素子基板を 縦向けに積層状に配置することで 設置占有面積当たりの発電量を向上させる。発電素子基板の微細加工プロセスの構築に向けて
シリコン基板とガラス基板の両基板に対する微細加工プロセスと,両者の接合プロセスについて検討を行い,試作微細加工実験を実施した。
(順不同) 戻る
|